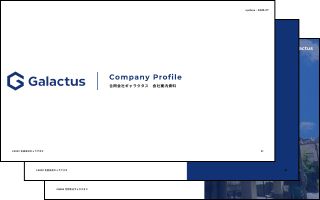【はじめに】なぜSEOチェックが必要なのか?
自社のWebサイトの集客やお問い合わせを増やしたいと考えたとき、「SEO対策」は非常に大切な施策となります。
しかし、いざ制作会社や専門のSEO会社に依頼しようとしても、「どこに課題があるのかわからない」「何を依頼すれば良いのか不明確」といった状況では、最適なパートナー選びも、効果的な施策の実行も難しくなります。
制作会社・SEO会社への依頼で失敗しないために
費用をかけて依頼したのに、期待した成果が出なかった…という事態はやはり避けたいものです。事前に自社サイトの状況を把握しておくことで、業者からの提案内容が妥当なのか、また自社が求める課題解決に本当に繋がるのかを判断する材料になります。専門知識をより多くもつ業者の言われるがままにならず、主体的にプロジェクトに関わるためにも、現状の理解は不可欠といえます。
例えば、「なんとなくサイトが古い気がする」「競合と比べてアクセスが少ない気がする」といった曖昧な認識ではなく、「表示速度が遅い」「特定のキーワードでの順位が低い」「スマホで見づらい」など、具体的な課題がわかれば、依頼内容も明確になるはずです。そうすると、より的確な見積もりや提案を受けることができ、費用対効果の高い施策に絞って取り組むことができます。
この記事でわかること
本記事では、SEOの専門知識がない方でも、自社サイトの現状を把握できるよう、具体的なチェックポイントを「技術編」「コンテンツ編」「外部要因編」に分けて解説します。これらのチェックを通じて、サイトの強み・弱みを理解し、制作会社やSEO会社に相談する際の基礎情報としてご活用ください。
私たちのような制作会社の視点も交えながら、実践的な内容をお届けします。
SEOチェックリスト
この章では、SEO対策の全体像を把握することを目的に、記事内で解説するすべてのチェックポイントを一覧で確認します。自社サイトの現状把握や、制作会社・SEO会社への相談時の参考資料としてご活用ください。
| 分類 | カテゴリ | チェック項目 |
|---|---|---|
| 技術編 | Googleの認識状況 | – インデックス状況の確認(Search Console) – robots.txtの設定確認 – XMLサイトマップの送信状況確認 |
| 技術編 | サイト構造 | – URLの正規化・階層構造の確認 – 内部リンクの適切な設置確認 – パンくずリストの設置確認 |
| 技術編 | 表示速度 | – PageSpeed Insightsでの計測 – Core Web Vitalsの確認 – 画像サイズの最適化確認 |
| 技術編 | モバイル対応 | – モバイルフレンドリーテストの実施 – レスポンシブデザインの確認 |
| 技術編 | セキュリティ | – HTTPS化の確認 |
| コンテンツ編 | キーワード戦略 | – ターゲットユーザーの検索ニーズ分析 – キーワード調査ツールの活用 – 対策キーワードの選定 |
| コンテンツ編 | コンテンツ品質 | – 検索意図との合致度確認 – E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の確認 – 独自性のあるコンテンツかの確認 – 読みやすさ(文章構成・装飾)の確認 |
| コンテンツ編 | 検索結果での訴求力 | – 魅力的なタイトル・ディスクリプションの作成 – 構造化データマークアップの活用 |
| コンテンツ編 | 画像最適化 | – alt属性の設定確認 – ファイル名の最適化確認 |
| 外部要因編 | 被リンクの質と量 | – 被リンクの質と量の確認(Search Console活用) – 関連性の高いサイトからのリンク獲得状況確認 |
| 外部要因編 | スパムリンク対策 | – スパムリンクの危険性確認 – リンク否認ツールの使い方確認 |
第1章:【技術編】サイトの土台は大丈夫?テクニカルSEOチェック
Webサイトが検索結果で適切に評価され、訪れたユーザーに快適な体験を提供するためには、まずその技術的な基盤、いわゆる「テクニカルSEO」が堅牢であることが不可欠です。デザインが洗練されていても、素晴らしいコンテンツが掲載されていても、検索エンジンがサイトの情報を正しく収集・理解できなかったり、ユーザーがスムーズにサイトを利用できなかったりすると、SEOの取り組み自体が水の泡となりかねません。
ここでは、サイトの見えない土台とも言える部分に焦点を当て、制作会社としても特に重要視するチェックポイントを詳しく見ていきます。
1-1. Googleはサイトを正しく認識できている?
大前提として、あなたのWebサイトがGoogle検索の結果に表示されるためには、Googleにその存在と内容を正しく認識されている必要があります。どれだけ有益な情報を提供していても、Googleのデータベースに登録されていなければ、検索ユーザーの目に触れる機会がないわけです。
まずは、Googleが自社サイトをどのように認識しているか、基本的な状況から確認することが第一歩です。
インデックス状況の確認方法(Search Console活用)
Googleの検索エンジンに登録・認識されている状態を「インデックス」されていると言います。
Google Search Consoleは、自社サイトのインデックス状況状態を把握し、Googleとコミュニケーションを取るための無料ツールです。
この中の「インデックス作成」>「ページ」セクションを定期的に確認することで、サイト内のページがGoogleにどれだけインデックスされているか、またインデックス登録を妨げるようなエラーが発生していないかを把握できます。
「インデックス登録済み」ページの数が想定よりも著しく少ない場合や、「未登録」のページに多くのエラーが表示されている場合は、サイトのクロールやインデックス登録プロセスに何らかの障害が発生している可能性が高いため、原因を特定し、適切に対処する必要があります。
robots.txt の設定は適切か
「robots.txt」ファイルは、検索エンジンのクローラー(サイト情報を収集するプログラム)に対して、サイト内のどのファイルやディレクトリにアクセスして良いか、あるいはアクセスを制限するかを指示する、いわば交通整理の役割を果たします。
この設定を誤ると、本来インデックスさせたい重要なページへのクローラーのアクセスを意図せずブロック (Disallow) してしまい、結果として検索結果に表示されなくなるという致命的な事態を招きかねません。特に注意したいのは、CSSやJavaScriptファイルへのアクセスをブロックしてしまうケースです。これらのファイルはサイトの見た目や動きを制御しており、Googleはこれらを読み込むことでページの内容や構造を正確に理解しようとします。これらをブロックすると、Googleはページを正しくレンダリングできず、モバイルフレンドリーでないと判断されたり、コンテンツの評価が適切に行われなかったりする可能性があります。
サイトのルートディレクトリ(例: https://example.com/robots.txt)に設置されているファイルの内容を確認し、意図しないアクセス制限がないか、慎重にチェックしてみてください。
XMLサイトマップは送信されているか
「XMLサイトマップ」は、サイト内に存在するページのリストや、その最終更新日などの情報を、検索エンジンが理解しやすい形式で記述したファイルです。
これをSearch Console経由でGoogleに送信することで、Googleはサイトの全体像を効率的に把握し、新しいページの発見や既存ページの更新情報を迅速に検知できるようになります。特にページ数が多い大規模サイトや、内部リンク構造が複雑なサイト、あるいは頻繁にコンテンツが更新されるサイトにとっては、クローラーを適切に誘導するために非常に重要です。
Search Consoleの「サイトマップ」セクションを確認し、サイトマップが送信されており、エラーなく正常に処理されているかを確認してみてください。もし未送信であれば、サイト構造に合わせて作成し、速やかに送信することをおすすめします。
1-2. サイト構造は検索エンジンにもユーザーにも親切?
サイトの構造、つまり情報がどのように整理され、ページ同士がどのように繋がっているかは、ユーザーの使いやすさ(ユーザビリティ)と検索エンジンの理解度(クローラビリティ)の両方に大きな影響を与えます。
直感的で論理的なサイト構造は、ユーザーが必要な情報に迷わずたどり着けるように助けるだけでなく、検索エンジンが各ページの内容とサイト全体のテーマ性を正確に評価するためにも不可欠です。
URLはわかりやすいか(正規化、階層構造)
各ページのURLは、そのページの内容を端的に示す、人間にも検索エンジンにも理解しやすい文字列であることが理想的です。
例えば、サービス紹介ページであれば https://example.com/service/seo/ のように、サイトの階層構造が反映された、シンプルで意味の通るURLが望ましいといえます。
一方で、https://example.com/page?id=123 のようなパラメータ付きのURLや、www の有無、index.html の有無、末尾のスラッシュの有無などで同一コンテンツにアクセスできる複数のURLが存在する状態は、「重複コンテンツ」とみなされ、検索エンジンからの評価が分散してしまう原因となります。
このような重複を避け、サイトとして最も評価を集めたい正規のURLを検索エンジンに明確に伝える「URLの正規化」が適切に行われているか、rel="canonical" タグの設定などを確認することが重要です。
内部リンクは適切に貼られているか
サイト内のページから別のページへと設置されたリンク、すなわち「内部リンク」は、ユーザーを関連性の高い情報へとスムーズに誘導し、サイト内での滞在時間や回遊率を高める上で重要な役割を果たします。同時に、検索エンジンにとっても、内部リンクはページ間の関連性を理解し、サイト内でどのページが重要視されているか(リンクが多く集まるページ=重要なページ、と判断される傾向がある)を判断するための重要な手がかりとなります。
コンテンツの内容に応じて関連ページへのリンクを自然な形で設置したり、全ページ共通のナビゲーション(グローバルナビゲーションやフッターナビゲーション)から主要なページへアクセスしやすくしたりするなど、戦略的な内部リンク設計が行われているかを見直しましょう。
パンくずリストは設置されているか
パンくずリストは、ユーザーが現在閲覧しているページがサイト全体のどの階層に位置するのかを示し、より上位のカテゴリページへ簡単に戻れるように設置されるナビゲーション要素です(例: ホーム > サービス > SEO対策)。
ユーザーがサイト内で迷子になるのを防ぐだけでなく、検索エンジンに対してもサイトの階層構造を明確に伝えるシグナルとなり、SEO上のメリットも期待できます。特にカテゴリが多岐にわたるECサイトや情報量の多いメディアサイトなどでは、ユーザビリティとクローラビリティの両面から、設置が強く推奨されます。
1-3. サイト表示速度は遅くない?
Webページの表示速度は、ユーザー体験を左右する最も重要な要素の一つと言っても過言ではありません。読み込みに時間がかかるページはユーザーにストレスを与え、目的を達成する前に離脱されてしまう(直帰率の上昇)大きな原因となります。さらに、Googleはページの表示速度をランキング要因の一つとして採用しており、遅いサイトは検索順位においても不利になる可能性があります。
PageSpeed Insightsでの計測と見方
Googleが提供する無料ツール「PageSpeed Insights」は、指定したURLの表示速度を分析し、具体的なパフォーマンススコア(0~100点)と改善のための提案を示してくれます。
特にモバイル環境でのスコアは近年ますます重要視される傾向にあります。単にスコアの高低に一喜一憂するのではなく、「改善できる項目」としてリストアップされる具体的な指摘内容(例: 「使用していない JavaScript の削減」「次世代フォーマットでの画像の配信」など)に注目し、技術的な改善策を検討するための重要な情報源として活用しましょう。
Core Web Vitalsの重要性
Core Web Vitals (コアウェブバイタル) は、Googleがページの健全性を示すために定義した、よりユーザーの実体験に近い指標群です。
具体的には、「LCP (Largest Contentful Paint):ページの主要コンテンツが表示されるまでの時間」、「FID (First Input Delay) → INP (Interaction to Next Paint) に移行中:ユーザーが最初に行った操作への応答性」、「CLS (Cumulative Layout Shift):ページの読み込み中に発生するレイアウトのずれの大きさ」の3つ(FIDからINPへの移行が進んでいます)を指します。
これらの指標はPageSpeed Insightsの結果内や、Search Consoleの「ウェブに関する主な指標」レポートで確認できます。全ての指標で「良好」な状態を目指すことが、ユーザー体験の向上とSEO評価の改善に繋がります。
画像サイズの最適化
ページの表示速度低下を招く最も一般的な原因の一つが、画像ファイルのサイズ(容量)が過大であることです。高画質の画像を多用したい気持ちは理解できますが、Webページで表示する上で必要十分なサイズにリサイズし、適切なファイル形式(JPEG、PNG、GIF、あるいはWebPのような軽量な次世代フォーマット)を選択し、専用ツールやサービスを用いて画質を損なわずにファイルサイズを圧縮することが重要です。
一つ一つの画像を見直し、最適化する地道な作業が、サイト全体の表示速度改善に大きく貢献します。
1-4. モバイルでも快適に見られる?
今やWebサイトへのアクセスの多くはスマートフォン経由であり、モバイル端末での閲覧に適した表示と操作性、いわゆる「モバイルフレンドリー」であることは、現代のWebサイトにとって必須要件です。
Googleもモバイルファーストインデックス(モバイル版ページの評価を主軸とする)を導入しており、モバイル対応はSEOの観点からも避けては通れません。
モバイルフレンドリーテストの実施
Googleが提供する「モバイルフレンドリーテスト」ツールを使えば、指定したURLのページがモバイル端末での閲覧に適しているかを簡単に判定できます。「このページはモバイル フレンドリーです」という結果が得られれば基本的には問題ありませんが、「モバイル フレンドリーではありません」と判定された場合は、指摘された問題点(例: 「コンテンツの幅が画面の幅を超えています」「クリック可能な要素同士が近すぎます」など)を確認し、デザインやコーディングの修正が必要です。
レスポンシブデザインの確認
現在のモバイル対応の主流は、閲覧しているデバイスの画面幅に応じて、ページのレイアウトや文字サイズ、画像の大きさなどが自動的に調整される「レスポンシブWebデザイン」です。
単にテストツールで合格するだけでなく、実際に様々なサイズのスマートフォンやタブレット端末で表示を確認し、文字が小さすぎて読みにくくないか、リンクやボタンがタップしにくい位置や大きさになっていないか、意図しない横スクロールが発生していないかなど、ユーザー視点での使いやすさを入念にチェックすることが大切です。
1-5. セキュリティは万全?
Webサイトのセキュリティ対策は、訪問するユーザーの個人情報や信頼を守る上で極めて重要であると同時に、検索エンジンからの評価にも影響を与える要素です。安全でないサイトはユーザーに敬遠され、Googleからも警告が表示されるなど、ビジネス機会の損失に繋がりかねません。
HTTPS化(SSL化)はされているか
HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure)は、Webサーバーとブラウザ間の通信をSSL/TLSという技術を用いて暗号化するプロトコルです。これにより、第三者によるデータの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐことができます。
Googleは数年前からHTTPSをランキングシグナルの一つとして利用しており、現在ではWebサイト全体をHTTPSで保護する「常時SSL化」が標準的なセキュリティ対策となっています。ブラウザのアドレスバーを確認し、URLが https:// で始まっており、鍵マークが表示されているかを確認しましょう。
もし未だに http:// で運用されている場合は、セキュリティリスクとSEO上のデメリットの両方があるため、可能な限り早急にSSL/TLS証明書を導入し、HTTPS化を完了させるべきです。
第2章:【コンテンツ編】ユーザーに価値を提供できている?コンテンツSEOチェック
テクニカルSEOによってサイトの基盤が整えられたなら、次はそのサイトを訪れるユーザーの心をつかむ「コンテンツ」そのものに目を向ける必要があります。検索エンジンは、ユーザーが検索行動を通じて解決したい疑問や満たしたい欲求にいかに的確に応えているかを、コンテンツ評価の重要な基準としています。Googleが提唱する「有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成」1という考え方は、まさにこの点を強調するものです。
ここでは、ユーザー満足度を高め、結果として検索エンジンからも評価されるコンテンツ作りのためのチェックポイントを見ていきましょう。
2-1. 狙うべきキーワードは明確?
効果的なコンテンツSEOの第一歩は、ターゲットとするユーザーがどのような言葉(キーワード)で情報を探しているのかを正確に把握することから始まります。
単に思いつきで記事を書くのではなく、ユーザーの検索ニーズに基づいたキーワードを選定し、そのキーワードで検索するユーザーが満足するコンテンツを提供することが重要です。
ターゲットユーザーの検索ニーズ分析
まず、自社のサービスや商品に関心を持つであろうユーザーが、どのような悩みや疑問を持っているかを想像してみましょう。彼らがGoogle検索を使う際、どのような言葉を入力するでしょうか?この「ユーザーの立場に立った想像力」が、キーワード戦略の出発点となります。
キーワード調査ツールの活用
想像だけでなく、実際の検索ボリューム(どれくらいの人がそのキーワードで検索しているか)や関連キーワードを客観的なデータに基づいて調査することも不可欠です。世の中には様々なキーワード調査ツール(無料・有料)が存在しますので、これらを活用して、ターゲットユーザーが実際に使っているキーワードや、関連性の高いサブキーワード、具体的な疑問を示す質問形式のキーワードなどをリストアップしましょう2。
対策キーワードの選定方法
リストアップしたキーワードの中から、実際にコンテンツで狙うべき「対策キーワード」を選定します。
選定の際には、
- 1. 関連性(自社の提供価値とコンテンツ内容に合っているか)
- 2. 検索ボリューム(一定数の検索需要があるか)
- 3. 検索意図(そのキーワードで検索するユーザーが求めている情報は何か?情報収集か、購入検討かなど)
- 4. 競合性(そのキーワードで上位表示を狙う競合サイトの強さ)
などを考慮し、バランスの取れたキーワードを選ぶことが肝心です。
特に「検索意図」の理解は重要で、ユーザーが何を知りたいのか、何を解決したいのかを深く理解することが、後述するコンテンツ作成の質に直結します。
2-2. コンテンツはユーザーを満足させられる?
対策キーワードが決まったら、次はそのキーワードで検索してきたユーザーを本当に満足させられる質の高いコンテンツを作成する必要があります。Googleは、ユーザーにとって価値の高いコンテンツを評価するための指標として「E-E-A-T」という概念を重視しています。
検索意図との合致度
最も重要なのは、ユーザーがそのキーワードで検索した「意図」にコンテンツが的確に応えられているか、という点です。例えば、「SEO対策 やり方」と検索するユーザーは、具体的な手順やノウハウを知りたいはずです。
それに対して、SEO対策の歴史や定義ばかりを説明するコンテンツでは、ユーザーの意図を満たしているとは言えません。ユーザーが検索に至った背景や、その先に求めているであろう答えを深く洞察し、それを提供するコンテンツ作りを心がけましょう。
情報の網羅性・専門性・信頼性 (E-E-A-T)
Googleがコンテンツ品質を評価する上で重視する「E-E-A-T」は、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字を取ったものです1。
経験(Experience)
実際に製品を使用した経験、サービスを利用した体験、ある場所を訪れた経験など、実体験に基づいた情報はユーザーにとって価値があります。
専門性(Expertise)
そのトピックに関する深い知識やスキルを持っていることが示されているか。専門用語を適切に使いつつも、分かりやすく解説できているかが問われます。
権威性(Authoritativeness)
その分野における第一人者として認識されているか、他の信頼できるサイトから情報源として引用されているかなどが指標となります。誰がコンテンツを作成したのか(著者情報)を明確にすることも有効です。
信頼性(Trustworthiness)
サイト全体の安全性(SSLなど)はもちろん、情報が正確であること、引用元が明記されていること、運営者情報が明確であることなどが信頼性の担保に繋がります。
特に、人々の幸福、健康、経済的安定、安全に大きな影響を与える可能性のある「YMYL (Your Money or Your Life)」と呼ばれる領域のトピックでは、E-E-A-Tがより一層厳しく評価されます。
独自性のあるコンテンツか
他のサイトにある情報を単にコピー&ペーストしたり、少し言い回しを変えただけのリライトコンテンツは、ユーザーにとってもGoogleにとっても価値が低いと判断されます。自社ならではの視点、独自の調査結果、具体的な事例、深い考察などを盛り込み、オリジナリティのある情報を提供することが重要です。
読みやすさ(文章構成、装飾)
どれだけ有益な情報が書かれていても、読みにくければユーザーは途中で離脱してしまいます。適切な見出し(h2, h3タグなど)を使って情報を構造化し、重要な箇所は太字にする、箇条書きや表を活用するなど、視覚的に分かりやすくする工夫が必要です。
また、一文が長すぎると読みにくくなるため、適度な長さで区切る、短文と長文を織り交ぜてリズムを作る34、専門用語ばかりでなく平易な言葉も使う、といった配慮も読みやすさ向上に繋がります。
2-3. 検索結果でクリックされる工夫は?
検索結果ページ(SERP)で上位に表示されたとしても、ユーザーにクリックされなければ意味がありません。検索結果上でユーザーの目を引き、クリックを促すための工夫も重要です。
魅力的なタイトル・ディスクリプションになっているか
タイトルタグ(<title>)
検索結果に表示されるページの「顔」とも言える部分です。ユーザーが検索したキーワードを含めつつ(可能であれば前方に入れると良いでしょう2)、ページの内容が具体的に分かり、かつクリックしたくなるような魅力的な言葉を選ぶことが重要です。数字を入れたり(例:「〇〇するための5つの方法」)、疑問形にしたり、ユーザーのメリットを提示したりする工夫が有効です。
ただし、検索結果での表示文字数には限りがあるため、30文字前後(PCの場合)を目安に、長すぎないように注意しましょう。
※ただし、記述したたちタイトルタグが検索結果上でそのまま採用されるとは限りません。
メタディスクリプション(<meta name="description">)
タイトルタグの下に表示されるページの要約文です。これもクリック率に影響を与える要素です2。ページの内容を正確に伝えつつ、ユーザーの興味関心を引き、「続きを読みたい」と思わせるような、簡潔で説得力のある文章を作成しましょう。ここにも自然な形で対策キーワードを含めることが推奨されます。
表示文字数はおよそ120文字程度(PCの場合)が目安です。
※ただし、記述したメタディスクリプションが検索結果上でそのまま採用されるとは限りません。
構造化データマークアップの活用
構造化データは、ページの内容を検索エンジンがより深く理解できるようにするためのマークアップです。これを適切に実装することで、検索結果に通常のタイトルやディスクリプションだけでなく、付加情報(レビュー評価の星、FAQ、レシピの調理時間、イベントの日時など)が表示される「リッチリザルト」となる可能性があります。
リッチリザルトは検索結果上で目立ちやすく、クリック率の向上が期待できます。
コンテンツの種類に応じて、適切な構造化データ(例: Article, FAQPage, Recipe, Eventスキーマなど)の導入を検討しましょう。
2-4. 画像は適切に使われている?
画像はコンテンツを視覚的に豊かにし、ユーザーの理解を助ける重要な要素ですが、SEOの観点からも最適化が必要です。
alt属性の設定
alt属性(代替テキスト)は、画像が表示されなかった場合や、スクリーンリーダー(音声読み上げソフト)を使用しているユーザーに対して、その画像の内容を伝えるためのテキストです。アクセシビリティの観点から非常に重要であると同時に、Googleが画像の内容を理解する手がかりにもなります。画像の内容を具体的かつ簡潔に記述したaltテキストを、全ての意味のある画像に設定しましょう。装飾目的の画像など、特に意味を持たない画像には空のalt=""を設定します。
ファイル名の最適化
画像のファイル名も、Googleが内容を理解するヒントになります。IMG_001.jpg や photo.png のようなデフォルト名や抽象的な名前ではなく、画像の内容を表す具体的で分かりやすいファイル名(例: seo-technical-checklist.jpg のように、単語間はハイフンで繋ぐのが一般的)にすることが推奨されます2。
第3章:【外部要因編】サイトは信頼されている?外部SEO(被リンク)チェック
サイト内部の技術的な要素やコンテンツの質を向上させるだけでなく、外部からの評価、特に他のWebサイトからの「被リンク」も、検索エンジンがサイトの信頼性や権威性を判断する上で重要な要素となります。
被リンクは、いわばインターネット上の「推薦状」のようなもので、質の高いサイトから多くの推薦(リンク)を受けているサイトは、検索エンジンからも高く評価される傾向にあります。
ただし、量だけでなく「質」が非常に重要であり、不自然なリンクや低品質なサイトからのリンクは、逆にペナルティの対象となるリスクもあります。
ここでは、外部からの評価、特に被リンクに関するチェックポイントを見ていきましょう。
3-1. どんなサイトからリンクされている?
自社サイトがどのようなサイトから、どれくらいの数のリンクを受けているかを把握することは、外部SEOの現状を知る第一歩です。
被リンクの質と量の確認方法 (Search Console活用)
Google Search Consoleの「リンク」レポートでは、自社サイトに向けられている外部リンク(被リンク)の情報を確認できます。「上位のリンク元サイト」セクションでは、どのサイトから多くリンクされているかが分かります。
単にリンクの数が多いだけでなく、リンク元のサイトが自社サイトのテーマと関連性が高いか、信頼できる情報源か(公的機関、業界団体、有名なメディアなど)、といった「質」の観点からもチェックすることが重要です。関連性が高く、信頼できるサイトからの自然なリンクは、SEOにおいてポジティブな影響を与えます。
関連性の高いサイトからのリンク獲得
理想的なのは、自社の業界やテーマに関連性の高い、質の高いコンテンツを持つサイトから、自然な形でリンクを獲得することです。例えば、有用な調査レポートを発表して引用されたり、業界イベントに関する質の高い記事を書いて関連サイトから紹介されたり、といった形です。
優れたコンテンツを作成し、その存在を適切に広める(コンテンツプロモーション)ことが、良質な被リンク獲得の王道と言えます。
意図的にリンクを購入したり、関連性のないサイトと相互リンクを大量に行ったりする行為は、Googleのガイドライン違反となる可能性が高いため避けるべきです。
3-2. 不自然・低品質なリンクはない?
過去のSEO対策や、第三者による意図しない行為によって、サイトに悪影響を及ぼす可能性のある不自然なリンクや低品質なリンク(スパムリンク)が付いている場合もあります。
これらを放置しておくと、検索順位の低下やペナルティの原因となる可能性があります。
スパムリンクの危険性
Googleは、検索順位を操作する目的で作成された不自然なリンクを厳しく取り締まっています。例えば、自動生成されたブログからの大量のリンク、海外の低品質なディレクトリサイトからのリンク、隠しテキストに含まれるリンクなどは、スパムリンクとみなされる代表例です。
Search Consoleのリンクレポートなどを定期的に確認し、明らかに不自然なリンクや、自社サイトとは全く関連性のない怪しいサイトからのリンクがないかをチェックしましょう。
リンク否認ツールの使い方
もし、自社サイトに悪影響を与えうる低品質なリンクを発見し、サイト運営者に連絡しても削除してもらえない場合は、Google Search Consoleの「リンク否認ツール」を利用して、特定のリンクをGoogleの評価対象から除外するよう申請することができます。ただし、このツールの使用は慎重に行う必要があり、誤って良質なリンクまで否認してしまうと、かえってサイトの評価を下げてしまう可能性もあります。
基本的には、Googleが不自然なリンクを自動的に判断してくれるケースも多いため、明らかなスパム行為による大量のリンクなど、深刻な場合に限定して利用を検討するのが良いでしょう。
不明な場合は専門家への相談をおすすめします。
第4章:【実践】自分でできる簡単チェックツール紹介
ここまで解説してきたSEOの各チェックポイントは、専門的な知識がなくても、便利なツールを活用することである程度は自分で確認・分析することが可能です。
ここでは、サイトの現状把握や課題発見に役立つ、代表的な無料ツールをご紹介します。まずはこれらのツールを使って、自社サイトの健康診断を始めてみましょう。
Google Search Console(グーグル サーチコンソール)
サーチコンソールは、サイト運営者にとって必須のツールです。
Google検索におけるサイトのパフォーマンス(表示回数、クリック数、掲載順位、検索キーワードなど)を監視できるだけでなく、インデックス状況の確認、XMLサイトマップの送信、モバイルユーザビリティの問題点、セキュリティの問題などをGoogleから直接通知・確認できます。
テクニカルSEOやコンテンツSEO、外部SEOの多くのチェック項目に関わる情報が得られるので、まずはこのツールにサイトを登録し、定期的にレポートを確認することから始めましょう。
Google Analytics(グーグル アナリティクス)
サイトへのアクセス状況を詳細に分析するためのツールです。
どのようなユーザーが(地域、年齢層、性別など)、どこから(検索エンジン、SNS、他のサイトなど)、どのページに、どれくらいの時間滞在し、どのような行動をとったのか、といったユーザー行動に関するデータを把握できます。SEO施策の効果測定や、ユーザーニーズの分析、コンテンツ改善点の発見などに不可欠なツールです。目標設定(コンバージョン設定)を行うことで、Webサイトがビジネス目標にどれだけ貢献しているかも計測できます。
PageSpeed Insights(ページスピード インサイト)
特定のページの表示速度を測定し、改善点を提案してくれるGoogleのツールです。URLを入力するだけで、PCとモバイルそれぞれにおけるパフォーマンススコアと、Core Web Vitalsの評価、そして具体的な改善提案(「改善できる項目」「診断」)を確認できます。
サイト表示速度のチェックと改善策の検討に役立ちます。
モバイルフレンドリーテスト
特定のページがモバイル端末での閲覧に適しているかどうかを判定するGoogleのツールです。URLを入力するだけで簡単にチェックでき、問題がある場合は具体的な修正箇所を指摘してくれます。
モバイル対応状況の基本的な確認に利用できます。
その他、役立つ無料・有料ツール
上記以外にも、特定のキーワードにおける競合サイトの分析、被リンクの詳細調査、より高度なサイト内部の技術的な問題点の検出など、特定の目的に特化した様々なSEOツールが存在します。
無料プランで試せるものも多いので、必要に応じて活用を検討してみるのも良いでしょう。(例: SEOチェキ!、ラッコキーワード、Ubersuggest、Semrush、Ahrefsなど)
第5章:チェック結果をどう活かすか?
各種ツールを使って自社サイトの現状をチェックしたら、その結果を具体的な改善アクションに繋げていくことが重要です。ただチェックして終わりではなく、得られた情報を整理し、次に何をすべきかを明確にしましょう。
課題の洗い出しと優先順位の付け方
各チェック項目とツールの分析結果から、自社サイトが抱える問題点や改善すべき点をリストアップします。例えば、「モバイル表示で一部レイアウトが崩れている」「特定の重要キーワードでの順位が低い」「表示速度が遅い」「主要なサービスページへの内部リンクが不足している」など、具体的に記述します。
洗い出した課題に対しては、その影響度(放置した場合のリスクや、改善した場合の効果の大きさ)と改善の実現可能性(必要な工数やコスト)を考慮して、優先順位を付けましょう。
全てを一度に解決しようとするのではなく、インパクトが大きく、比較的取り組みやすいものから着手するのが現実的です。
具体的な改善アクションプランの検討
優先順位の高い課題に対して、具体的な改善策を検討します。
「モバイル表示のレイアウト崩れ」であれば、どのページのどの部分をどのように修正するのか。「キーワード順位の低さ」であれば、該当ページのコンテンツ内容の見直し(情報量の追加、E-E-A-Tの強化など)や、タイトル・見出しの最適化、関連する内部リンクの追加などを検討します。「表示速度の遅さ」であれば、画像サイズの圧縮、不要なプラグインの停止、サーバー環境の見直しなどを考えます。
誰が、いつまでに、何を行うのか、具体的なアクションプランに落とし込むことが重要です。
制作会社・SEO会社への効果的な情報共有方法
自社での対応が難しい課題や、より専門的な分析・改善が必要な場合は、外部の制作会社やSEO会社への依頼を検討することになります。その際、ここまでのチェックで得られた情報は、非常に有効なコミュニケーションツールとなります。依頼時には、以下の情報を明確に伝えることで、業者側も的確な提案や見積もりをしやすくなり、認識の齟齬を防ぐことができます。
現状の課題
「Search Consoleで〇〇のエラーが出ている」「PageSpeed Insightsでモバイルのスコアが〇〇点だった」「△△というキーワードで上位表示させたいが、現状〇〇位である」など、客観的なデータや具体的な状況を伝えましょう。
達成したい目標 (KPI)
「特定のキーワードで〇位以内に入りたい」「Webサイト経由の問い合わせ件数を〇〇%増やしたい」「〇〇ページの直帰率を改善したい」など、具体的かつ測定可能な目標(KPI:重要業績評価指標)を設定し、共有します。
予算感
どの程度の予算を考えているのかを事前に伝えておくことで、予算内で実現可能な施策の提案を受けやすくなります。
まとめ
今回のチェックポイントを通じて、自社サイトの現状について、ある程度の理解が深まったのではないでしょうか。SEO対策は一度行えば終わりではなく、検索エンジンのアルゴリズム変動や競合サイトの動向、ユーザーニーズの変化に合わせて、継続的にサイトの状態をチェックし、改善を続けていくことが重要です。
定期的なSEOチェックでサイトの健康状態を保つ
今回ご紹介したようなチェックを定期的に(例えば月に1回、四半期に1回など)行い、サイトの健康状態を把握する習慣をつけましょう。問題点を早期に発見し、対処することで、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。
課題を明確にして、最適なパートナーを選ぼう
自社サイトの課題が具体的になっていれば、制作会社やSEO会社に依頼する際にも、より的確な要望を伝えることができ、自社の目標達成に本当に貢献してくれるパートナーを見つけやすくなります。本記事が、そのための第一歩となれば幸いです。
参考文献
- 有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成 | Google 検索セントラル | ドキュメント | Google for Developers
- SEO Writing: 16 Tips for Creating SEO-Optimized Content | Semrush Blog
- Sentence Length: How to Improve Your Research Paper Readability | Paperpal Blog
- How to Captivate Readers With a Dazzling Loooong Sentence | Enchanting Marketing
- Image SEO: How to optimize your alt text and title text | Yoast
- How to Write Alt Text for Images for SEO (3 Easy Tips) | AIOSEO